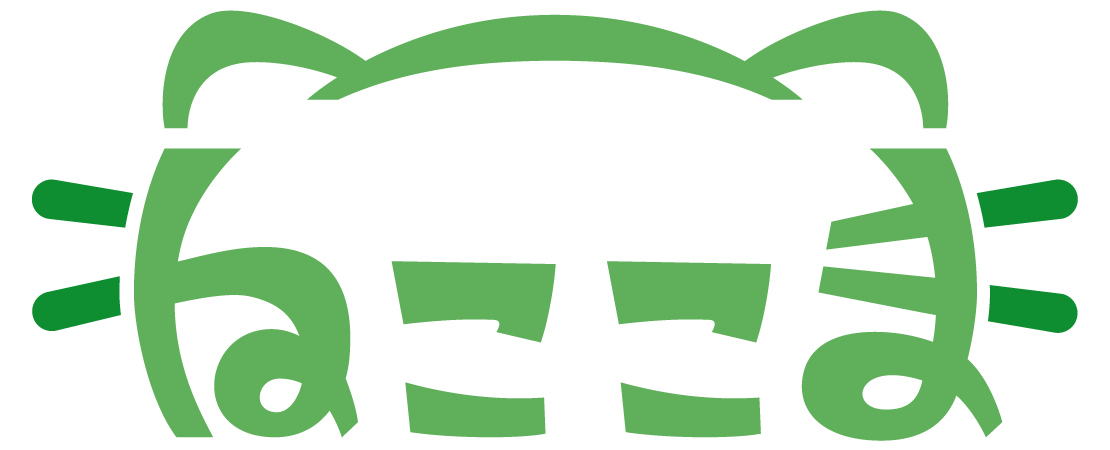猫がご飯を吐いた!
原因は?どうすれば吐かなくなるの?
こんな疑問について解説します。
- 猫がご飯を吐く原因
- 吐かないようにする対策
- 吐いた時の対処法
- 病院を受診した方がいい嘔吐
- 吐いたもので分かること
猫は元々吐きやすい動物です。結論として、猫がご飯を吐く理由は一度に食べる量が多かったり、早食いが原因であることが多いです。
対策として一度に与えるご飯を少量にし、1日4回以上に分けて与えてください。空腹の時間を減らすことで満腹感を満たし、早食い防止の効果もあります。 また、食器の位置を高くすることで食道にご飯が詰まるのを防ぐことができます。
吐いてしまった時は、何を吐いたのか中身をよく確認してください。

具体的に解説していきます!

この記事を書いている私は「キャットケアスペシャリスト」資格を取得しています。Twitterのフォロワー数は5000人以上おり、「猫のスペシャリスト」として猫に関する知識を発信中です。
当記事の内容については学術的根拠をもとに十分な配慮をしておりますが、その効果を保証するものではありません。疑問点はかかりつけ医にご相談をお願いします。
前提知識|なぜ猫はよく吐くの?

猫は身体の構造上吐きやすい
猫はもともと吐きやすい動物です。人間と違って猫は四足歩行なので、胃の高さが口と同じ位置にあります。身体の構造上、人間に比べて猫が吐きやすいことが分かりますね。
獲物の骨や毛を吐くため
猫は小鳥やネズミといった獲物を丸のみしていました。骨や被毛は消化できないので、そのまま排泄するか吐き出す必要があります。そのため、嘔吐しやすいよう猫の食道は「横紋筋」と呼ばれる意識的に動かせる筋肉で構成されていたり、咽頭反射(オエッとなる反応)が弱いのではないかと考えられています。
毛玉を吐くため
猫は毎日毛づくろいに多くの時間を使います。猫の舌はザラザラとした突起が反り返っており、絡みとった毛を飲み込んでしまいます。すると胃に毛玉が溜まり、それを吐き出す必要があります。
吐く行為は「吐出」と「嘔吐」がある

- 吐出 (としゅつ)
- 胃に入る前に吐いてしまう現象。未消化の物を前に飛ばすように吐き出す。食後すぐに吐く。
- 嘔吐 (おうと)
- 胃や腸にある物を吐いてしまう現象。胃液が混じった消化物を下向きに吐き出す。吐く前兆がある。
吐出は食べた物が食道を通りにくくなっている時に起こります。一度に与えるご飯の量を減らしたり、フードの粒を小さくすることで解決する可能性があります。何らかの問題で食道の一部が狭くなってしまう「食道狭窄(しょくどうきょうさく)」という症状が原因になることもあります。
特に注意すべきは嘔吐です。吐出に比べて疾患が隠れている可能性が高くなります。猫の元気がなかったり、1週間に2回以上吐く場合などは病院に連れて行きましょう。
キャットフードを吐く原因11個

猫は吐きやすい動物であり、フードを吐く原因も様々です。まずは心当たりのある原因はないか確認してみましょう。
①一度に食べる量が多い
ドライフードは胃の中で水分を吸収して膨張します。もしフードの量が多ければ胃が圧迫され、吐き戻しの原因になります。食後に水を飲んでしまうのもドライフードがふやけて膨張する原因となることが多いです。
②早食いをしている
未消化の物を吐く場合、早食いが原因である可能性が高いです。空気も一緒に飲み込んでしまい、食べた物を押し出し吐いてしまうこともあります。本来猫は自分で狩りをし獲物を捕まえていました。すると獲物を横取りされたり、食事中は無防備になってしまいます。なので野生の本能が残り、早食いをしてしまう猫が多いようです。多頭飼いでも他の猫にご飯を取られまいと早食いをしてしまうことがあります。
③フードが合っていない、アレルギーがある
食後30分以内に吐いてしまう場合、フードが合っていない可能性があります。まずはフードを少量にして与えてみてください。ご飯が合っていなければ少量でも吐いてしまいます。アレルギーが原因で吐くこともあり、自己判断せず獣医師に相談してみることが大切です。
④胃に毛玉が溜まっている
猫は胃に溜まった毛玉を吐き出すという習性があります。猫の舌はザラザラとしており、毛づくろいで絡みとった毛を飲み込んでしまうためです。毛玉は吐き出すか、そのまま排泄されるかのどちらかですが、胃や腸で詰まってしまうこともあります。すると食欲不振や便秘になる「毛球症」になってしまうので、定期的なブラッシングを心がけましょう。
⑤猫草を食べている
猫草を食べると尖った葉が胃を刺激し、毛玉を吐き出すのではないかと考えられています。猫草は猫にとって嗜好品であり、与えなくても何かの栄養が不足するわけではありません。単に草の噛み心地を楽しんでいることもあるようです。
⑥ストレスがある
引越しをした、家族構成が変わった、新入りの猫が来たなど、生活環境によるストレスが原因になることがあります。模様替えをしただけでも縄張り意識の強い猫にとってはストレスがかかります。欲求不満の原因を見つけ、猫が落ち着ける環境を与えてあげましょう。
⑦食後に運動をしている
食事の後に走り回ったり、おもちゃで遊ぼうと動き回り吐いてしまうことがあります。遊ぶ時間はお腹が空いているご飯前にしましょう。空腹時は「獲物を捕まえよう」という狩猟本能が高まり、よく遊んでくれる傾向にあります。獲物を捕まえてから食事をする、という流れは猫の満足度も向上します。
⑧異物を誤飲している
異物を飲んでしまった際に体からそれを出そうとして吐くことがあります。何も吐かないのに吐く仕草を繰り返すことも。腸で詰まってしまうと腸が塞がれる「腸閉塞」を起こし、手術が必要になる場合があります。吐いた物の中に異物がないか、身の回りで無くなった物はないかを確認し、もし誤飲の可能性があればすぐに病院を受診しましょう。飲み込んだものが小さくても念のため獣医師に相談してください。
⑨中毒症状になっている
もし猫がよだれを垂らしていたり、震えや下痢、激しく吐くといった症状があったら中毒を起こしている可能性があります。早急に病院へ連れて行きましょう。猫には危険な植物が700種類以上あると言われています。特にユリは猛毒で、少量の摂取や、花瓶の水を飲んだだけで死に至ることある危険な植物です。また、ネギや玉ねぎも食べると命に関わるので絶対に与えないようにしましょう。
⑩寄生虫がいる
嘔吐物の中に5〜10cmくらいの白い糸状の虫がいないか確認してください。それは猫回虫という寄生虫で、猫に寄生しているとそれを嘔吐することがあります。猫回虫は猫の体内を移動しながら成長し、小腸で卵を産んで便と一緒に排泄されます。猫回虫は人間にも感染するので、トイレ掃除の後はしっかりと手を洗いましょう。猫とキスをすることで人が感染することもあります。
⑪疾患がある
胃や腸などに疾患があったり、熱中症でも嘔吐をしてしまうことがあります。1週間のうちに何度も吐く場合は危険信号。いつ、何を吐いたか、その時の様子や吐く頻度などを記録し獣医師に相談しましょう。また、体重が減少している場合も診察をおすすめします。食事量は同じなのに1〜3ヶ月で体重が約5%以上減っていたら疾患が隠れている可能性があります。
【5%減少した体重を知りたい時】
元の体重×0.95=5%減少した体重
(例)4.7kgの猫の体重が5%減ったら?
4.7×0.95=4.47kg

4.7kgの猫が4.47kgになったら注意かも、と計算できます
少しでも不安があれば自己判断せず病院へ連れて行きましょう。
猫の吐き戻しを防ぐ対策10個

①食事の回数を増やす
食事の回数を増やし、1度に与える量を減らしましょう。1日に与えるご飯の量を決め、それを1日4回以上に分けて与えてください。自動給餌器があればセットした時間に決まった量のフードが出るので、外出時でもご飯を与えることができます。空腹の時間を減らすことで満腹感を満たし、早食い防止の効果もあります。

②早食い防止の食器に変える
早食いをしてしまう猫には突起のある早食い防止のお皿が効果的です。一気に食べることが出来ないので吐き戻しを軽減できます。食器は猫が食べやすいよう高さのあるものを選びましょう。
③お皿の位置を高くする
猫は四足歩行なので口と胃は同じ高さにあります。しかしお皿が低いと胃の位置より口元が下がってしまうため、食べた物が逆流する原因となってしまいます。お腹も圧迫されるので猫にとっては辛い姿勢です。関節が弱りやすい高齢猫にも負担となってしまいます。台の上にお皿を置いたり、高さのある食器を用意して食事がしやすいよう工夫してあげましょう。
④フードを変える
フードを変えてみるのは手軽にできる方法です。選ぶ時の注意点として、安すぎるフードは避ける、添加物や油分の多いものは避ける、年齢に合ったフードにするなどがあります。毛玉を吐きやすい猫には、飲み込んだ毛の排出を促してくれる毛玉ケア用のフードもオススメです。愛猫が食べてくれるフードを探してあげましょう。
⑤粒の小さいフードを与える
フードの粒を小さくすることで吐き戻しを軽減できる可能性があります。猫はあまり噛まずに食事をするため、大きい粒をそのまま飲み込むと喉に詰まりやすくなってしまいます。フードは粒の小さいものを選ぶか、砕いて小さくしたものを与えましょう。
キャットフードの「モグニャン」は一粒が8mmほどの小粒なフードです。人間も食べられる高品質な白身魚を65%も使用しており、香料や着色料は不使用。さらに欧州ペットフード工業会連合 (FEDIAF)の厳しい基準にも合格しており、安心して猫に与えることができます。
⑥ご飯の横取りが起きないようにする
多頭飼いでは他の猫にご飯を取られないよう早食いをすることがあります。横取りが起きないよう食事場所を猫によって分け、安心してご飯が食べられる環境を与えてあげましょう。他の猫のご飯を横取りしていないか日頃から観察してみてください。
⑦ストレスのない環境にする
引越しや家族構成の変化、新入り猫が来たなどでストレスを感じ、吐いてしまうことがあります。猫が安心できるお気に入りの場所や、隠れられる場所を用意してあげましょう。特に部屋を見渡せる高い場所があると猫が安心します。高所はテリトリーで異常がないか確認できるのでリラックスできるようです。
⑧ブラッシングをする
猫は毛づくろいで絡みとった毛を飲み込んでしまいます。定期的なブラッシングをして飲み込む毛の量を軽減させましょう。特に毛量が多い長毛種の猫や、毛づくろいの頻度が減る高齢猫はブラッシングに気を遣ってあげてください。ブラッシングを嫌がる猫には毛玉ケア用のサプリを与えるのも効果的です。
⑨誤飲しそうなものは片付ける
猫が口に入れそうな物は全て片付けましょう。誤飲で多い物は、ヘアゴム、輪ゴム、紐、糸、アクセサリー、ビニール袋などです。お子さんがいる家庭に多いウレタンマットも噛みちぎって食べてしまうことがあり危険です。ペットショップで販売しているネズミの玩具も誤飲が非常に多いので注意してください。胃や腸に詰まれば手術が必要になることもあり、命に関わります。
⑩病院に相談する
自己判断せず獣医師に相談してみることも大切です。「吐く原因はこれだろう」と思い込んで対策をしていても、他に原因があることもあります。疾患が隠れている可能性もあるので、少しでも心配事があれば病院での診察を受けましょう。
吐いた後の対処法

猫が吐いてしまったら必ず吐いた中身を確認してください。危険な嘔吐を見極め、いつもと様子が違うなと感じたら早めに病院へ連れて行きましょう。
「様子を見ていい嘔吐」と「危険な嘔吐」

危険な嘔吐の見極めが大切です
吐いた物や色で分かること

- 未消化のフード
- 食べ過ぎや早食いが原因であることがほとんどです。一度に与えるご飯の量を減らしたり、早食い防止の食器に変えて対策しましょう。お皿の位置を高くすると食べた物が食道で詰まらず、逆流しにくくなります。
- 消化されたペースト状のフード
- ご飯が合っていない、食物アレルギー、誤飲、疾患など、原因はさまざまです。いきなり新しいフードに切り替えると食べ慣れていなくて嘔吐することがあります。キャットフードは茶色のものが多いので、嘔吐物も茶色のものになります。元気や食欲がない、お腹が張っている、週に2回以上吐く、様子がおかしいと思ったら動物病院へ連れて行きましょう。
- 透明な液体や白い泡
- 胃液です。空腹が原因であることが多いです。空腹の時間を減らせるよう、ご飯を与える時間を調整しましょう。嘔吐を繰り返すようであれば胃や食道の不調など、別の要因も考えられるので病院を受診してください。
- 黄色の液体
- 胆汁です。空腹が原因で嘔吐してしまうことがあります。対策として、1日に与えるご飯の量を決め、それを1日4回以上に分けて与えてください。食事回数を増やすことで空腹の時間が減ります。改善しない場合は別の原因が考えられるので、獣医師に相談しましょう。
- ピンクや赤、赤黒い液体
- 体内から出血している可能性があります。嘔吐物の写真を撮り、すぐに病院を受診しましょう。血液は胃酸と混ざると黒っぽくなります。誤飲の可能性はないかも確認してください。
嘔吐物の内容や時間を記録をする

いつ、何を吐いたか、誤飲の可能性はないか、吐いた時の様子など出来るだけメモを残しましょう。もし病院を受診することになった際、そのような記録があれば嘔吐の原因を特定しやすくなります。
実際の嘔吐物や写真があると診察がスムーズになります。
診察で獣医師が一番困るのは飼い主さんからの情報がない時です。例えば「何をいつ吐いたか覚えていない」「妻が猫の世話をしていて詳しい内容は分からない」など。

獣医さんは飼い主さんからの情報が頼りです!
まとめ|ご飯の与え方を工夫しよう

猫はもともと吐きやすい動物です。キャットフードを吐く理由として一度に食べる量が多かったり、早食いが原因であることが多いです。その場合はご飯を1日4回以上に分けて、満腹感を持続させるようにしましょう。また、危険な嘔吐を見極めるために吐いたものをよく確認してください。

この記事でのポイントは6つ!
- 一度に与えるフードの量を減らす
- 早食い防止の食器に替える
- 食器の位置を高くする
- フードを変えてみる
- 吐いたものをよく観察する
- 週に2回以上吐く、元気や食欲がない、様子がおかしい時は病院へ
どうしても症状が改善しない時は自己判断せず獣医師に相談してください。吐いてしまう猫ちゃん本人も辛いですからね。 少しでも改善することを祈っております。
 【プロが解説】猫が布を噛む、食べる原因と対策9つ。誤食時の対処法は?
【プロが解説】猫が布を噛む、食べる原因と対策9つ。誤食時の対処法は?
☆この記事がイイネと思ったら応援のクリックをお願いします☆